Qualification acquisition support
各大学視察報告

フリンダース大学

1 キャンパスツアー
フリンダース大学のキャンパスの広さは257ヘクタール。キャンパス内にはスポーツの施設などがある。キャプテンマテューフリンダー船長が、大学の名前の由来である。南オーストラリア州の海岸線を探索した初めての探検家で、インべスゲーターという船のキャプテンであった。

3月にオープンした新しい建物である。「プラザ」は2,000人が座れる野外劇場で、大きなスクリーンがある。教育、法律、物理、化学などの学部の建物がある。
車いすを使う学生もいるのでアクセシビリティーに配慮している。エレベーターもきちんと配置して、障害のある学生にも使いやすいキャンパスにしている。オーストラリア人の学生、留学生のなかにも、車いすを使っている学生がかなりいる。
オーストラリア政府は、外国人留学生で障害のある人たちに対して特別に奨学金を提供している。目が見えない、歩けない、自国では金銭的な理由で電動車いすを使えないけれども、政府が提供することでオーストラリアでの留学を経験できる。
フリンダース大学は、障害留学生の約半分の12人を受け入れている。大学は、障害学生に対して適切なサポートサービスを提供していることを大変誇りに思っている。
郵便局、旅行代理店なども大学のなかにある。図書館が5か所配置されている。数百万点の蔵書がある。ここは100%学生のための建物である。楽に時間を過ごしたいときなどに使用している。24時間オープンなので好きなときに利用している。
25,000人の学生中に留学生が4,500人いる。彼らは必ずしもキャンパスで勉強しているわけではなく、自国で勉強している学生がいるので、教員が外国に出かけて行ってプログラムを展開している。
学生食堂では、安いけれども健康によい食べものを提供する業者を選んでいる。学生用のキッチンもある。トースター、レンジなどがあり、簡単な料理ができる施設を提供している。
「フリンダースコネクト」と呼んでいるところでは、勉強での相談、授業料の支払いの相談を受けるなどの窓口が一か所にまとまっている。ピーク時には1日2000件のコンタクトがある。勉強できるスペースも設けている。
どの建物、図書館でも、学生が静かな場所で勉強したいときに利用できる配置をしている。グループでの研究、勉強もできるスペースである。どの部屋でも充電ができるほか、高速のインターネット環境が整備されている。
1970年以降女性専用の部屋を設ける大学が増えてきた。女性専用の部屋なので安心する女性たちも多い。子どもがいる学生のために授乳する部屋も設けている。
2 ランチミーティング
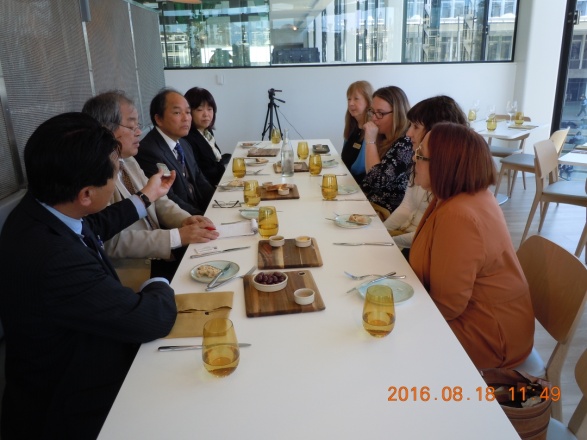
ランチミーティングでUp The Hill Programコーディネーターのアドライン氏らと意見交換を行った。その一問一答は次の通りである。
──この大学に社会福祉学部のような学部はあるのか。
ヘルスカンセリング&ディサバリティーサービスという学部がある。ソーシャルワーカーになるためのコースがあり、それが福祉にあたると思う。ソーシャルワークとかソーシャルポリシーとかソーシャルプランニングという言い方をする。
知的障害の学生たちは、トピックを自由に選ぶことができる。そのトピックに関して行なわれるレクチャーは普通の学生に行われるレクチャーなので、担当者がそうした講義をする先生やメンターなどをコーディネートして、そういう学生たちがきちんと講義を受けられるような体制をつくっていく。
──知的障害の学生が好む勉強にはどういうものがあるか。
いろいろな学生たちがいてさまざまなトピックを選ぶが、1ついえることは、たとえば、ある学生が歴史に興味があると選ぶトピックはみんな歴史関係のトピックになるとか、芸術が好きであればそれに関係するトピックを選ぶという傾向がある。これまでの学生で、障害というトピックに関心をもった人もいれば、先住民の芸術や国際関係に興味をもつ学生もいた。
──3年間のプログラムを終えて資格など卒業のメリットはあるか。
卒業時に学位はないが修了証書を与える。また、私たちに対してプレゼンテーションを行うことも決まっている。3年間を終えた段階で、通常の学生たちといっしょに卒業式に出席する。そのときは卒業生の帽子やガウンを着て参加をする形を取っている。
3年間修了するということは非常に大きな達成感があるものだと思う。3年間で選ぶトピックは1つだけかもしれないが、ほかの普通の学生たちと同じように3年間続けて勉学に励むことは、それだけのコミットメントをしたわけだ。それをやり続けたというのはやはり大変な偉業だと思う。
──途中でリタイヤする人はいるか。
いる。健康面や就職が決まったとか、別のことをやりたいなどの理由があってのことだと思う。中退者のデータを見ると、普通の学生と障害のある学生で数字は違うけれども、割合としてはほぼ同じになっている。障害のある学生が辞める率が極端に高いとか低いというわけではない。
実は今年、知的障害の学生で仕事の実習に初めて参加した学生が出てきた(本節5、6参照)。その学生は女性だが、実際に小学校の特別支援学級で、障害のある人たちと1対1で仕事をする経験を積んだ。知的障害の学生がこういう形で参加するのは初めてだ。とてもうまくいった。その経験はすごく楽しかったといっている。彼女自身は作業療法士になる目標があるので、その職業に行くわけではない。
受け入れる学生の知的障害の程度、たとえばIQの値を考慮することはなくて、応募するときに知的障害という診断を受けたという書類があれば受け入れている。障害者であることが確認できれば、大学としては、その人が学生としてここで勉強していく上での対人関係ができる能力があるかどうかだけを審査する。
──定員を超えた入学希望者がいた場合は何を基準に決めるのか。
1学年で6人を受け入れている。資金的な問題があるので6人と限っている。私自身は週に2日しか仕事をしていない。受け取っている資金では週2日しか雇えないからだ。
そういう状況なので入学待機リストがある。約2年間待たなければならない。12人くらいが待機リストにいる。1人が出ていけば1人を受け入れる状況だ。
──年齢層は高卒ばかりではなくさまざまか。
必ずしも高校を卒業してすぐという人ばかりではない。ある程度経験を積んでから来る人もいるので、かなり年上の人もいる。30〜50歳。何歳からでも始められるのはいいことだと思う。
──アップザヒルプログラムは何年前にスタートしたのか。
1999年に正式にスタートした。それ以前の1997年にパイロットプロジェクトをスタートして改善をしてきていた。
──最初から6人は変わっていないのか。
最初は参加者4人で始まった。正式にスタートできる資金が確保できたということで1999年にこのプログラムがスタートしたが、その間継続的に行ってきて少しずつ改善していった。
──3年間で学生たちの一番成長するところ変化するところはどこか。
まずは自信をもつところだ。知的障害の学生たちもそうだが、メンターをする学生たちも経験を通して自信をもつことができる。みんなにとってとてもいい経験ができる。
それから会話力。話をする機会が格段に増える。メンターと話さないといけない、先生とも話さなければいけない。機会が増えてくることで技術も上達するのだと思う。時には知的障害である学生がメンターである学生たちに「こうするべきだ」とアドバイスをすることもある。
だから成功した1つの理由としては、人工的につくられた環境ではなく、毎日の生活のなかでいろいろなことをしなければいけないというオプションがたくさん出てきたことだと思う。フォーマルでもインフォーマルな形でも、学びの場があるということだと思う。
──知的障害の学生たちもサークル活動や行事に参加することがあるか。
関心があれば当然参加する。2人の学生はメンターもいっしょに毎週木曜日にヨガのクラスに参加している。アートが好きな学生が多いので、ギャラリーに行くとか実際に絵を描く学生たちも多く、そういう行事に積極的に参加する学生たちもいる。
──フリンダース大学の20年という歴史のなかで、学生たちが成長している姿を見て、オーストラリアのほかの大学が真似をしたいという意見や広がりはあるか。
シドニー大学はそういうプログラムをすでにスタートしている。ほかにはメルボルンで似たようなことがスタートしたと聞いたことはあるが、大学ではなくてコミュニティのほうに移ったというようなことを聞いた。同じようなことをしている大学はないと思う。
我々がどういうことをやっているかということについて、関心をもっている大学は必ずある。ただ、やはり大学という制度のなかでやろうと思うと、どうしても制度的な要素が障壁になってしまうから、それを上手く実際に行うためには、かなりトリッキーというか難しいところがある。
アップザヒルプログラムは、本人ばかりではなく参加者の親にとってもすごく影響の大きなものだと思う。というのは、障害があるから兄弟と同じようには大学に行けないだろうと思っていたのが、そういう機会をできたことで、それ自体をとても喜んでいる。そして、本人が満足していると同時に家族も、自分の障害のある子どもが大学に行って勉強していることに大変な満足感を感じていると思う。
プログラムを実施している我々の大学のなかでさえ、障壁になるものがまだかなりある。例をあげれば、講師である先生たちが、学生たちが勉強したいトピックに必ずしもアクセスできるわけではないということがある。また、障害のある学生たちを受け入れない先生がかなりいる。そうした学生たちと接する機会がないことから、端的にいえば恐怖感が先生たちのなかにあるのではないかと思う。
──日本の大学の先生たちも知的障害者を理解していないと思う。日本とフリンダース大学の違いは、日本はまったく受け入れていないがここは受け入れているから何らかの触れ合う機会があり、そこで変わってくる可能性を感じる。
大学でとてもいいと思うのは、障害者と仕事をしていく人たちの専門家を育てるコースがあるということ。それだけに学生たちも、障害に対する理解が一般よりも深いと思うし、その考え方に広がりをもたせることができると思う。障害をポジティブに捉える考え方という土壌があるからできているのではないかと思う。
「障害者政策及び実践」というコースがあり、学びたいという海外からの留学生がかなりいる。留学生を受け入れることは、我々にとっても非常に学びの機会だと思う。インクルーシブな社会なのか、どういう状況が起こっているのかも、留学生を通して学ぶことができている。
そんな理由で、オーストラリアと日本の間でさらに活発に交流ができていろいろな交換ができたらいいと思う。私たちの一番の上司は南アメリカに行って、そこの大学と交流をして情報交換をしている。そんな形で日本とも何かできればいいと思う。アフリカ、東南アジアからの留学生もいる。
──最初にフリンダース大学が知的障害者を受け入れるようになったきっかけは何かあるか。
知的障害のある家族が、これをつくるきっかけになったと聞いている。やはり家族の力が、こうしたプログラムをスタートさせる土台をつくることはよくあることだと思う。
プログラムが始まる段階で、この大学の誰かがリサーチをしてその結果をマスターの論文にしたのがきっかけになったのかもしれない。こういう仕事をする上でリサーチはとても重要だし、そうしたなかから生まれてくる情報がいろいろな事をする上でとても重要な役割を果たしている。
3 フリンダース大学のプレゼンテーション

太平洋プロジェクトは、知的障害がある人たちに対して大学の経験をする機会を提供するのが目的だ。
使命は、フリンダース大学におけるインクルーシブであり、支援を提供する機会をつくるときの柱となっているのが大学環境にアクセスできることだ。大学環境へアクセスするということは、具体的には社会的スキル、社会性を培うこと。我々のプロジェクトに参加する知的障害者たちが教育的機会だけではなく社会的な機会も得ることができること、そのなかにはヨガの教室に通うということも含まれている。
目的は、支援が受けられる環境、学生たちが大学でさまざまなトピックを調べることができることだ。メンターやいろいろな人たちが手伝い、その彼らの協力によって入学手続きをするなどさまざまな準備をする。こうして自立性を培う。また社会的なできごとに参加していく、メンターを通して別の大学の友人を紹介してもらい関係を築いていくことや、大学で行われるさまざまな交流の機会としてのイベントに参加するということだ。
そういう経験を通して学生たちは自信を構築していき、関係を維持していく。大学ではさまざまなトピックを扱っているが、そのトピックを学生たちが選ぶことによってそれに関連するレクチャーに参加する、あるいは個人のチュートリアルの研究をする。
その背景にある考え方は、1人ひとりのユニークな能力を最大限に引き出していこうとして、まず個人が何に関心があるかを明らかにする。歴史に関心がある人もいれば、アートに関心をもつ人もいる。その個人の関心と提供されるトピックをうまく組み合わせることによって、学びの提供をしている。
コースへの加入資格は、知的障害という診断を受けている人で、実際にその条件のもとで可能性のある入学希望者には、面談でその人が本当に大学で学ぶことに関心があるのかどうかの確認をする。また、それに伴う個人的なスキルがあるのかの確認をしていく。
このプロジェクトを行う資金を得る条件として、入学者はまず、知的障害者であることをクリアした後の面談の段階で、本当にこの学生が大学に行きたいのかどうかの確認がある。これはとても重要なポイントだ。もし本当の意味での関心がなければ、大学に来る意味がない。
その他の条件として、大学の生活が自分でできること、講義に出席するだけの能力があること、学びの環境のなかでほかの学生の妨害をしたり邪魔をしたりしないことも入っている。
メンターはIOEセンターからさまざまな形で支援を受ける。メンターとなる人のバックグランドは、障害のある人の教育に関わる学習、医療科学、行動科学、心理学、教育学などを専攻している学生たちだ。
メンターとなる学生たちは、知的障害の学生たちが専攻している科目を取っていないことが条件になっている。それは、その知的障害の学生たちが勉強している科目について、その内容を教える立場にはならないという理由からだ。あくまでもその学生がレクチャーなどに出席するのを支援するのであって、学習内容を教えるのではない。
就職活動をしている学生たちは、それまでに知的障害の人たちと何らかの形でいっしょに仕事をした経験のない人たちだ。そういう形を取ることによって、普通の学生たちが大学で学んでいるセオリーを、この経験を通して実践に移していくわけだ。実際に障害のある人たちと仕事をすることによって、さまざまな経験を積むわけだ。
4 レイチェルさん(Up The Hill Project 2014年卒業生)のプレゼンテーション

私は非常にラッキーだった。フリンダース大学で3年間、大学生を経験することができた。2011年から2014年のことだ。本当に大好きなプロジェクトだった。その前の4年間、待機者として入学を待たなければいけなかった。しかし、待つだけの価値のあるすばらしいプロジェクトコースだったと思う。
もちろんこの学生生活を可能にするためには、たくさんの人たちの支援が必要だった。そしてその人たちの援助を受け交通手段、食事、パーソナルケアなどに、非常に親切な職員たちに支えられた。
また、すばらしいメンターに会うこともできた。メンターには、講義やチュートリアルなどで、私の代わりにメモを取ってもらったり、プレゼンテーションをするためにその準備をしてもらったりと、さまざまな形で支援を受けた。
大学のなかで生活をしていると、私のような人物に対してどのように接したらいいのか、どういう関係をもったらいいのかよくわからない、という人たちがかなりいた。学生ばかりではなく、教える側の教師陣にもそういう人たちがいた。しかしメンターを通して、我々のような人とどのように関わったらいいか、さまざまなモデルを示すことができたと思っている。
3年間で6種類の科目を勉強した。私が特に好きだったのは、障害についての勉強だ。私の知っている人たちのなかに、そうしたことに深く関わっている人たちが多くいたからだ。
私にとって学生生活のハイライトと呼べるものは、ほかの学生あるいはメンターと知り合うことができたこと。そうした経験を通して私は自分自身に対する自信を高めることができたと思う。そうした経験の前の段階では、何をするにしても神経がボロボロになるくらい緊張してしまったが、自信を得ることによって変わってきた。
実は、言語聴覚士のサラさんと出会い、彼女からコミュニケーションを取る装置などさまざまなアドバイスを受けた。その中でiPadを使ってコミュニケーションを取る方法を教えてもらった。コミュニケーションを取ることでは、過去にかなりいやな経験をしたことがあるので、それを解決していくためのアドバイスだった。
いま私は、適切な選択をできるようになった。つまり、自分はどこに行きたいのか、何をしたいのかを決められるようになったし、食事でどういうソースがほしいかもはっきり主張することができるようになった。
医者に会ったときには、いま自分が不安に思っていること、あるいは必要としていることを伝えることができるようになった。何を着たいのか、テレビのどういう番組を見たいのかなども選択できる。また、自分の過去について話すことができるばかりでなく、将来的に自分はどうしたいのか、どういう目的をもっているのかという話もできるようになった。
もっとも重要なことは、約50年間にわたって他人が私の代弁者として話をしていたのが、いま私は自分自身の言葉を使って話せるようになったことだ。これによって私の自由が非常に広がった。
5 ケリーさん(Up The Hill Project 3年生)のプレゼンテーション

私がこのアップザヒルプロジェクトで終えた科目は、神経疾患のリハビリに関する導入、コミュニティリハビリおよび後天性の脳損傷、パーソナリティー、社会的心理学、個人的な交流およびグループとしてのスキル、障害を通じての発達、そしてプラティカルアイだった。
私はクリスティビーチスペシャルオプションスクールで、メンターにより支援を受けていた。自閉症やダウン症に関連する人と人との間の関係性、あるいはリサーチに関する資料などについての勉強をした。そしてそれに必要なさまざまなこと、たとえば算数の九九を全部勉強した。それを学生と先生との活動のなかで行い、メンターによって支えられた。必要な科目に関するアクティビティはすべて終了した。
いろいろなミーティングにも参加した。たとえば私のメンターであるアマンダーパーマンさんとのミーティングや、「スペシャルオプションプリンスファー」というタイトルのシャドンジャクソンさん、フリンダース大学講師のシャネンマーハンさん、アップザヒルプログラムのコーディネーターのヨネンリミさんのミーティングに出席をした。実はそうしたミーティングのときに、議題の準備をして議事録も私自身が取った。
私は特に2人の学生といっしょに勉強するということが多かったが、勉強するのがとても楽しかった。というのは、学友と経験を積むことによって、特に障害のなかでも2つの側面について、とても強く関心を抱くようになったからだ。
1人目は、バスケット部とスローイングボールというゲームをするのが大好きなダウン症の青年だった。もう1人は自閉症の学生で、その人の観察も行った。彼の障害はさらに複雑で、理解するのもさらに難しいものだった。
アップザヒルプログラムは、私にとって夢が現実となったものだと思う。
18年前、私はある障害のある人たちのグループの手伝いをしたことがある。グループは、心理学専攻の学生、障害に関する内容を専攻していた学生たちが支えていた。そうした学生たちを私自身がとてもよく知るようになり、彼らがやっていることや、私が友だちのグループメンバーに対してやっていることに、非常に強いインスピレーションを得た。グループには約50人のメンバーがおり25人のボランティアがいた。私が見た限りでは、私自身が障害のある人たちの助けになりたいと感じたわけだ。
このアップザヒルプログラムを見つける前は、私自身どこに行けば何を学べるのかがわからなかった。しかしいま、大学の学生となり来年卒業を迎えるが、できれば卒業後障害者介護の分野で仕事が見つかればいいと考えている。
私が実習を行ったのはセンサリールームといって、五感をすべて使っていろいろなことを探る部屋だ。学生の1人を外に連れて行き、いっしょにバスケットボールをした場所だ。彼にとってはすばらしい経験だった。
アップザヒルプログラムで私の使った時間は、すべてがとても貴重なものだ。私は昔から、いろいろなことを調べるリサーチ活動が大好きだった。しかしこのプログラムで行ったことは、それまでの私の人生とは比べものにならないほど充実したリサーチ活動だった。
私自身はこのプログラムをずっと続けていたい気持ちはあるが、それはできない。というのは、ほかの誰かもまた自分自身がどういう人間なのかを、彼ら自身でほかの人たちに証明する機会を与えられるだけの資格があるからだ。
私の支援をしたメンターたちは、私の友だちになった。大学以外のさまざまな交流の場をいっしょに楽しんでいる。私自身は学びの新しい方法を学んだし、またとてもすばらしい人たちからいろいろなことを学んだと思う。メンターになった友だちも、私たちに同じことをいっていた。
来年私は、特にアドボカシーとメンター制度についての勉強を続けていきたいと思っている。
6 イボンさん(ケリーの母)のプレゼンテーション
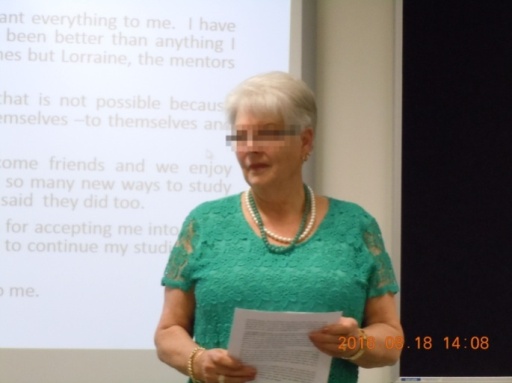
ケリーは44歳。ダウン症だ。民間の福祉サービス事業所で、彼女のいろいろな世話をしてもらっている。そこの会社で週3回、彼女に仕事をする機会を与えてもらっている。アップザヒルプログラムに参加をする一方で、そうした職業の経験を積んでいる。
ケリーは小さいときからハッピーで好奇心がとても強く、何についても調べてみたい子どもだった。小学校の頃からさまざまな研究活動が大好きで、イルカについての調査や野生の馬についての研究などもしていた。
成長していくにつれて、他人に対する優しさが前に出てくるようになり、障害のある人たちに対しても、何らかの手伝いをしたいという思いが強くなった。読み書きやいろいろなスキルがあるが、そうしたところを習得する手伝いをしたいということだった。
高校を卒業した時点で私と夫が、彼女が学び続けるためにはどういう機関があるのかを考えた。高校を卒業した人たちが行く「テイク」という職業専門学校があるが、そこでコンピューター、英語、数学などのコースを取り勉強をした。あるときは、特別支援学級の知的障害児クラスでボランティアとして仕事に行き、その仕事が大好きになった。
通信教育も受け始めた。補助教員になるためのコースで勉強もした。そのコースは有料だったが、奨学金を得られて一部の授業料をカバーできた。このコースを18か月間続けたが、残念ながらコースすべては完了できなかった。いろいろ出された課題などにレポートを提出し、優秀なレポートとして賞を受けたにもかかわらず、コース自体が途中で廃止されてしまったからだ。
しかしその段階で、コースを提供していたところから、ほかにすばらしいプログラムを提供しているところがあると紹介された。ケリーも関心をもったし、夫も私も求めていたそのものだった。それがこの大学でのプロジェクトだった。
そして実際に大学に通い、大学での経験を通じてさまざまなことを学んでいるわけだが、ほかの学生と同じように目的をもった生活を送っているということに、私たちは大変大きな喜びを感じている。できればこの大学で得た知識を、ほかの人たちを支援するために使ってほしいと思っているし、彼女もそのつもりでいる。
このアップザヒルプログラムに関わる関係者の誰もから、ケリーの1つひとつのステップでさまざまな形での支援を提供してもらった。本当にすばらしい人たちに囲まれて、彼女はこの3年間を過ごしてきた。
この3年間は夢だと考えている。まだまだケリーにとって学ぶものがたくさんあるにもかかわらず、終わりの時期はすぐに来てしまう。この3年間でケリーの自分に対する自信は、目を見張るほど高まった。多くの友達をつることができた。宿題や課題なども自分からすすんで行っていた。彼女の世界は急激に広がったと感じている。
親として、自信に満ちた大学生の子どもが将来のある人生を歩いていることを嬉しく感じている。これこそがアップザヒルプログラムがケリーにしてくれたことだ。メンターのおかげで講堂に入りレクチャーを聞き、家でしなければならない復習まで手伝ってもらった。メンターのおかげで3年間さまざまなことを学び、さらに学びたいという気持ちを維持している。
メンターで関係が始まった人たちは、いまはケリーの友達となり、いっしょに映画に行ったりコンサートに行ったり、会っておしゃべりをしたりする関係になっている。このプログラムの非常に重要な点だと思っている。
ケリーは、ここが限界だということを受け入れられずに、その枠をさらに広げていこうという子だ。最終の実習が、クリスティズビーチという名前の学校で行われた。障害のある学生たちが、こうした実習を行うのは過去になかった。まったく新しい領域だ。
そのため、コーディネーターのドメインさんも大変尽力されたと理解している。この実習は、非常に大きな成功を収めることができた。ケリー自身も、学生たちといっしょにいろいろなことをすることが楽しくて仕方がないというところがあった。また事務関係の仕事についても大変な興味を示した。この実習が実施されどのように終わったのかについて、関係者1人ひとりが強い印象を受けた。
このプログラムはケリーにとって非常に貴重な経験であり、貴重な体験をする機会を与えるものだった。なかでも彼女自身に、ほかの人たちに対してやればできることを証明する機会を与えてもらったと感じている。
このようなものは、ほかにはないと思う。やはり障害があるとはいえ、何かしたいことがあり、また学びたいことがあり、達成したいことがあれば、それを成すための機会は絶対に与えられるべきだと、私は考えている。







