Staff essay
スタッフエッセイ
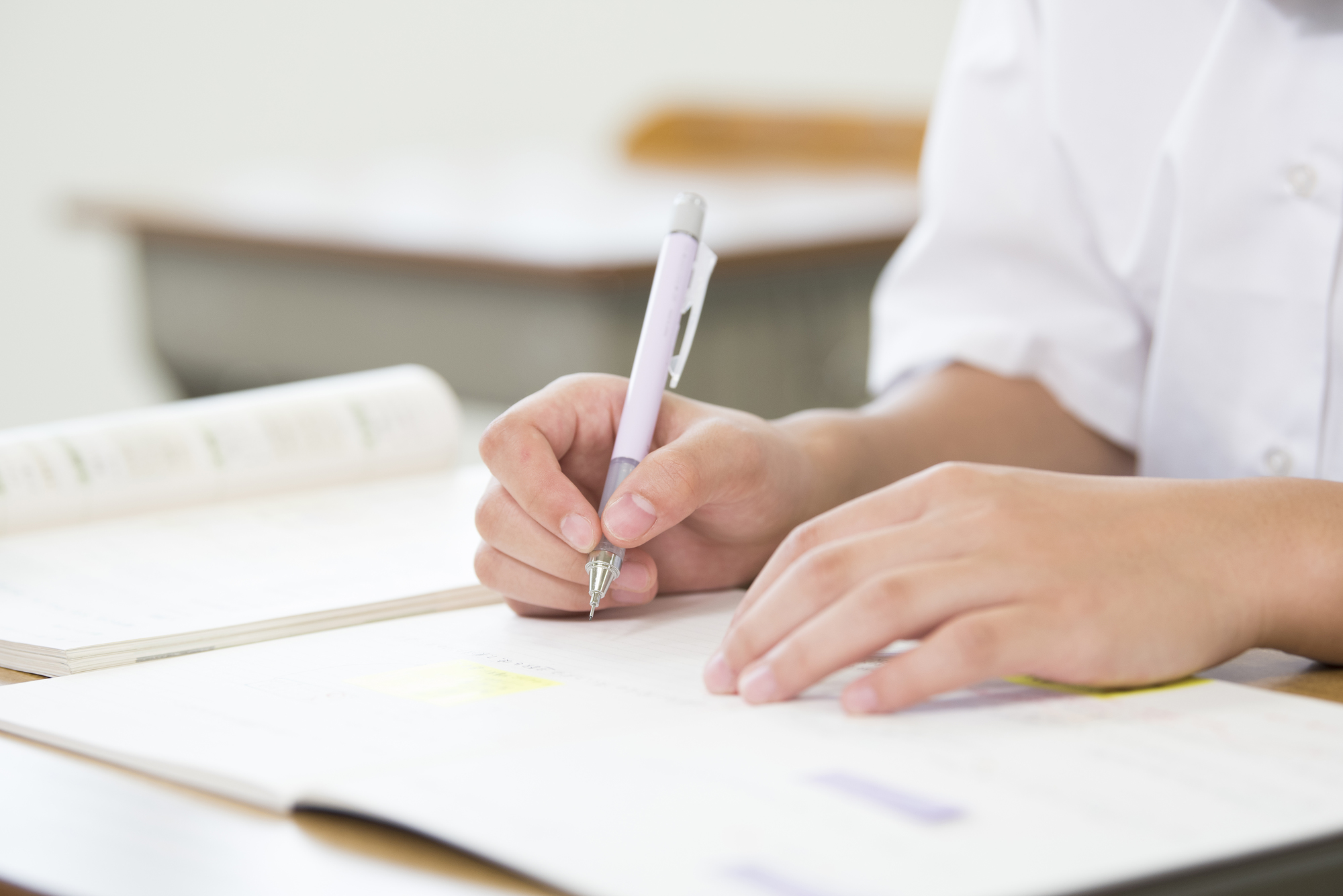
Essay
エッセイ
<23>「互いを高めある場所」
<22>ねぇねぇ、またアイロンの授業やろうね!
<21>一抹の寂しさを感じながらも、頼もしい顔が何とも嬉しかった
<20>学生たちがより良い人生を歩んでいくために日々考えています
<19>ゆたかカレッジでの学生の成長で思うこと
<18>Aさんの紙袋
<17>ゆたかカレッジでの2週間で感じたこと
<16>あたたかい「がんばって」
<15>小さな見えない成長を積み重ねるゆたかカレッジ
<14>プラス思考になろう
<13>一年目のゆたかカレッジ
<12>涙をこらえて
<11>トレードマークの笑顔
<10>今青年期らしい成長の姿
<9>今日は昨日よりもっと跳びたい
<8>頑張ろうとしている姿
<7>「寄り添う」ということ
<6>とあるささいなことから・・・
<5>ゆたかカレッジで得たもの
<4>少しずつ姿を見せる「隠れていた力」や「忍耐」
<3>ゆっくり着々と
<2>自分を見つめるということ
<1>カレッジで成長するということ




