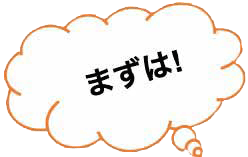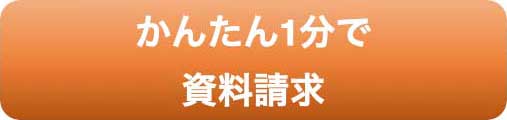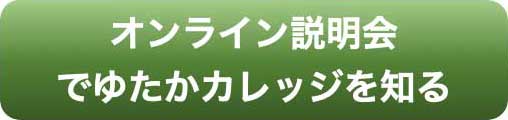《福祉コラムVol.32》知的障害者、ADHDにリスクのある合併症について解説!
2022.10.20

知的障害者とADHDの関係性はご存じでしょうか。
また、合併状はなぜ起こるのか考えたことはあるでしょうか。
合併症が起こると成長や生活に対して影響が出てしまい、1人では困難なことがたくさん予想されます。
そのため、生活は支援が必要になります。
知的障害やADHD、合併症についてを理解し、どんな事を必要としているのか考えていきましょう。
知的障害とADHDにリスクのある合併症について詳しく説明していきます。
知的障害とADHDの関係性
知的障害と併発しやすい疾患にADHD(注意欠如・多動症)があります。
知的障害の特性から、ADHD(注意欠如・多動症)の併発に気付きにくい場合もありますので、行動の観察が必要になります。
ADHD(注意欠如・多動症)は、不注意、多動性、衝動性の3症状を主な特徴とする生まれつきの、神経発達症郡の一つになります。
ADHDについて
ADHD(注意欠如・多動症)について詳しく説明していきます。
原因は不明ですが、脳に何らかの機能異常があるためです。
18歳以下で約5%存在しています。
大脳の前頭前野は、思考・判断・注意・計画・自己抑制・コニュニケーションなどの活動に関わっています。
ADHD(注意欠如・多動症)は、この前頭前野の機能調節に偏りがあるため、不注意、多動性、衝動性といった症状があらわれるのです。
また、脳内では神経伝達物質が刺激や情報を隣の神経細胞に伝えています。
神経伝達物質には、ノルアドレナリンやドーパミンなどの意欲に関わるもの・セロトニンなどの抑制に関わるものがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)は、こういった神経伝達物質の量が少ないことでしっかりと情報伝達が出来ていないとも考えられています。
主にこのような症状があります。
<不注意に関する症状>
- 活動に集中できない
- 途中でやめてしまう
- 順序を立ててやり遂げることが出来ない
- すぐに気が散ってしまう
- 待つことが出来ない
- 約束を忘れてしまう
- 忘れ物やなくし物が多い
<多動性、衝動性に関する症状>
- 手足をそわそわと動かしている
- じっとしていられない
- 静かにしていていられない
- 急に席を離れてしまう・急に走り出す
- 順番が待てずぬかしてしまう
ADHD(注意欠如・多動症)の治療にはどんなものがあるのか
ADHD(注意欠如・多動症)の治療は2つあり「療育」と「薬による治療」です。
<療育とは>
ADHD(注意欠如・多動症)の子供が生活しやすい環境を作ったり、社会参加をするために必要なスキルを身につけるための支援を行います。
- 刺激を減らす
- 課題や目標に集中できるようにする
- 集団行動するためのコミュニケーションの取り方
- 自己コントロールの仕方
<薬による治療とは>
原因は、脳に何らかの機能異常があり、脳内の神経伝達物質の働きがうまくいっていないためと言われています。
ドーパミンという神経伝達物質の伝達を助ける(メチルフェニデート徐放剤)と、ノルアドレナリンという神経伝達物質の伝達を助ける(アトモキセチン)があります。
この2つの薬剤は、それぞれ効果時期や副作用が違うため、個人差に合わせうまく使い分ける必要があります。
合併症はなぜ起こる?
合併症が起こる原因はさまざまな要因が関係しています。
脳の中枢神経系疾患が原因の1つと言われており、こういった脳の疾患のある合併症が起こる場合が多いです。
知的障害やADHDがかかるリスクのある合併症
知的障害の方やADHDの人がかかりやすいリスクのある合併症を詳しく説明していきます。
<知的障害、ADHDの人がかかりやすい合併症>
- 抑うつ
- 双極性障害
- 不安障害
このような精神疾患を併発するケースが多いです。
<抑うつとは>
抑うつとは、気分が落ち込んでしまい何もする気になれない・憂鬱な気分などの気持ちが滅入るような心の状態が多くなることです。
原因は疾患・薬・性格・環境・ストレスなどによっても起こる可能性があります。
また、抑うつの症状はさまざまで、動悸や便秘などの自律神経症状を伴うことも多いです。
興味や関心がなくなってしまう
興味や娯楽など今まで楽しいと思っていたことが楽しく感じられなくなります。
今まで興味があったことへの関心が薄れてしまいます。
睡眠状態
眠れず不眠になってしまいます。
睡眠の途中で目が覚めてしまう・寝つきが悪いなどの睡眠障害が出てきます。
食欲と体重の変化があらわれる
食欲の低下から体重の減少や、逆に食欲が増して体重が増加してしまいます。
つらい、死にたい、消えたいといった悲観的な気持ちが多い
迷惑をかけてつらい、みんなと同じことができなくて消えたい・死にたいといった悲観的な気持ちになる場合があります。
<双極性障害とは>
双極性障害とは、気分が高まったり落ち込んだりを繰り返す状態です。
躁状態(気分が高まっている状態)では、周囲の人にかまわず話しかけたり、全く眠れず活動することがあります。
- ハイテンション
- 自信満々
- 開放的
- 怒る
- 睡眠時間が短い
うつ状態(気分が落ち込んでいる状態)では、何もする気になれず、今まで興味があったことに関心がなくなったり、食欲のあるなしで体重に変化があらわれます。
うつ病に似ていますが、双極性障害は躁状態とうつ状態を繰り返す病気になりますので、全く違う病気になり治療薬も変わってきます。
- 食欲が減る
- やる気がない
- 落ち込む
- 興味がなくなる
- 無気力
<不安障害について>
初めての出来事や予測できないことに不安を感じることは誰でもあります。
しかし、不安が過度になりすぎてしまったり、不安な状態が持続してしまい日常生活に支障が出てしまう場合があります。
危険でないものにまで不安や恐怖を感じてしまう事もあります。
心の症状
- 緊張しておりリラックスできない
- 疲れやすい
- 怒りやすい
体の症状
- 頭痛
- 便秘・下痢
- めまい
- 痺れ
まとめ
知的障害やADHDを持つ人は、さまざまな合併症にかかりやすいことが理解できました。
特に知的障害、ADHDの人がかかりやすい合併症は、
- 抑うつ
- 双極性障害
- 不安障害
このような3点があります。
日常生活は1人で生活するのが困難で、支援を必要としている人が多いです。
個人差がありますが、どんな事を必要としているのか考え、関わり支援していきましょう。
関連記事

2022.09.16
《福祉コラムVol.15》知的障害者の結婚はどうなる?その状況について詳しく解説!
昨今、多くの方の結婚における価値観が変化する中、知的障害者の結婚について考えたことはありますでしょうか? 知的障害者は結婚をしてみたいと思っているのでしょうか。 そもそも、結婚している方が多いのでしょ[...]

2022.09.29
《福祉コラムVol.19》知的障害児とは?幼児期からの行動特性なども詳しく解説!
小さい子どものうちでも、知的障害の診断を受けることができます。 知的障害とは、発達期(18歳以下)までに生じた知的機能障害により、認知能力の発達が全体的に遅れた水準の状態をいいます。 診断を受けた子た[...]

2022.08.09
《福祉コラムVol.9》重度知的障害者とは?
重度知的障害者は、どんな人のことを示すのかご存知でしょうか。 どのような特徴があり、介助や支援が必要なのでしょうか。 また、重度知的障害と診断がおりた場合どのような福祉サービスや、サポートを受けること[...]