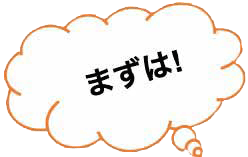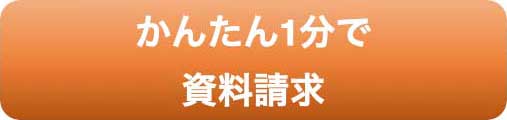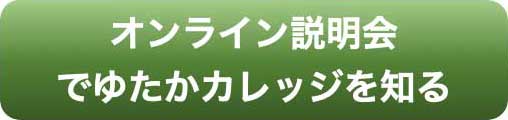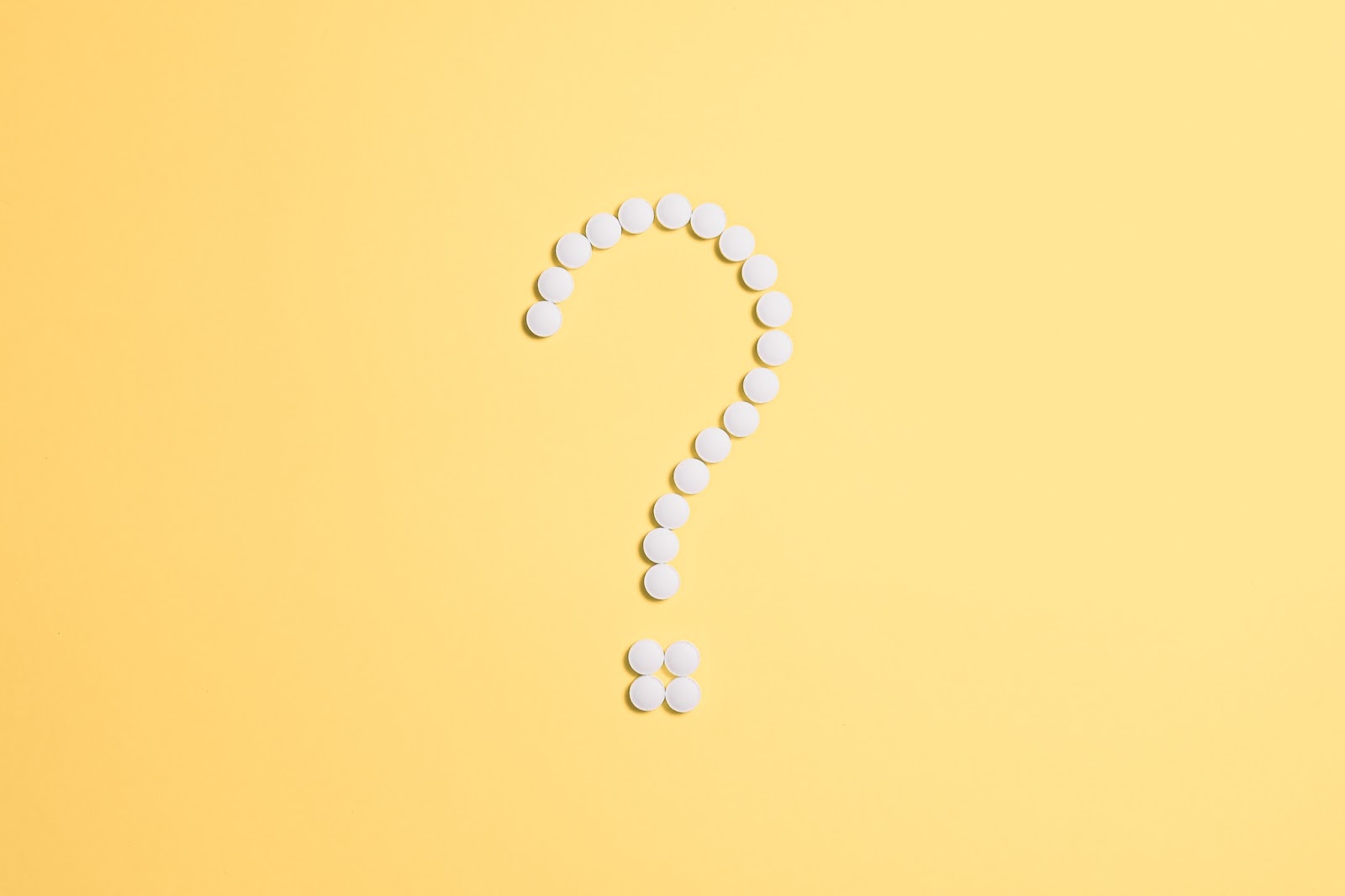《福祉コラムVol.22》2歳児の知的障害はどこでわかる?チェックリストで紹介
2022.10.04

「知的障害はどこでわかるのでしょうか」
「どんな症状なのだろう」
言葉は聞いた事があるけど、内容まで詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか。
特に小さなお子さんがいる人は、特に気になるでしょう。
2歳児の発達と知的障害のチェックリストを作りましたので紹介していきます。
知的障害には、発達期(幼少期から青年期・18歳以下)にあらわれ、知的能力が75未満、日常生活・社会生活での適応能力が低いといった特徴があります。
知的障害のあらわれ方には個人差がありますのでご注意ください。
【2歳児の知的障害】2歳児の発達の個人差
2歳児の発達において詳しく説明していきます。
知的障害は、幼い頃からあらわれている事がありますが、0歳の時点では分かりません。
子供によって診断する時期は違いますが、小学生になる頃には知的障害のほとんどが診断されています。
また、1歳半と3歳児健診でわかる事もあります。
1歳児健診について
1歳半頃になると興味があるものを指差したり言葉を発します。
言葉は単語の「ワンワン」等の2語を話します。
例えば診断内容はこのようなものがあります
- 「ワンワン」などの2語を話せる
- 近くにある物の名前がわかる・指をさせる
- 名前を呼ぶと振り向ける
- 「わんわんのぬいぐるみ持って来て」等の指示が通る
3歳児健診について
3歳は生活の中で簡単な会話が話せます。
記憶力や集中力も身についてきます。
例えば診断内容はこのようなものがあります
- 自分の名前と年齢を伝えられる
- 「ママ好き」などの二語文を話せる
- 自分から質問ができる
こちらの内容に成長が当てはまっていればしっかりと成長している証拠です。
2歳児は筋肉や骨格が発達し動きが活発になります。
よちよちとした歩きがしっかりとした歩きに変わります。
また、走る事も出来ます。
話せる言葉も増え短文ではありますが、コミュニケーションが取れるようになります。
診断の内容で、当てはまらなかったり、不安になる人もいらっしゃるかも知れませんが、子供の成長には個人差があります。
発達の個人差は自然な現象になります。
もしかしたら発達障害かもと早々に思う必要はありません。
健診をしっかり受け、周囲の子供との関わり、日常生活の中での発達を観察し主観的・客観的な視点を持ちましょう。
もしも、その中で悩んだり不安な点は専門家に相談していきましょう。
【2歳児の知的障害】発達チェックリスト
2歳児の発達についてチェックリストを作りました。
また、2歳児の知的障害についても説明していきます。
2歳児の発達チェックリスト
運動面について
1歳よりも筋肉や骨格がしっかりしてくるため、動きが活発になります。
- よちよち歩きではなく、しっかり歩け走れる
- ボールが投げられる
- 階段の昇り降りがつかまらずにできる
- マットや布団の上などで横転ができる
言語面について
2歳児は話せる言葉が増えます。
個人差がありますが、単語でのコミュニケーションが取れるようになります。
挨拶から(おはよう・ありがとう)二語文(ママすき・これ食べたい)等を話せるようになります。
- 自分の名前や年齢を伝えられる
- 挨拶ができる
- 名前を呼ばれると振り向ける
- 二語文を使い会話ができる
生活面について
1歳児は手づかみで食べていた食事も、2歳児になるとスプーンやフォークを使って食べるようになります。
洋服を自分で着たり、おもちゃの片付けもできるようになってきます。
大人に手伝ってもらい排泄も少しずつではありますが出来るようになります。
1人で出来る事も増えて来ますので、見守りや出来ないところは助けてあげたりと「子供の力」を伸ばしていきましょう。
- 食事でスプーンやフォークが使える
- 自分で洋服を着ることが出来る
- おもちゃを片付けられる
- 手伝ってもらい排泄ができる
心について
自我が発達し、「やりたい・やりたくない」がはっきりしてきます。
嫌なことは、泣いたり怒ったりと表現豊かになります。
また、自分以外の人間に興味を持ち始めます。
さまざまなことが自分で出来る様になり、周囲との関わりも出て来ます。
2歳は精神的な自立の時期にもなりますので、周囲は褒めたり温かく見守るなどして関わって行くことが必要になります。
- やりたい・やりたくないがはっきりする
- 自分でなんでもやりたがる
- こだわりを持つようになる
- 興味を持つ範囲が広がり、友達と一緒に楽しく遊べる
身体面について
固い食べ物や大きな食材を食べられるようになります。
自分でさまざまなものが食べられるようになりますので、食事が楽しみになります。
また、母乳やミルクだけではなく、食事量が増えますので体は成長していきます。
- 食事が食べられる(幼児食)
- 乳歯が生えそろう
- 身長・体重共に成長期
これらが一般的な2歳児の発達傾向になります。
発達には個人差がありますので当てはまらない場合もあります。
1〜3歳児に知的障害があるとあらわれること
- ひとり遊びが多く友達と遊ばない
- 言葉の発達、歩き出しが遅い
- お気に入りのおもちゃでしか遊ばない
- 約束事をすぐ忘れる
- 気に入らない事があると怒ったり泣く、パニックになる
これらに当てはまると、発達障害の可能性があります。
個人差がありますが、2歳児は体も心も発達している途中です。
そのため、診断がはっきりされるとは限りません。
障害があるとは、言い切れないため今後の成長を見届けていきましょう。
もしも、不安がある方は一度専門家に相談してみましょう。
まとめ
1〜3歳児に知的障害があるとあらわれること
- ひとり遊びが多く友達と遊ばない
- 言葉の発達、歩き出しが遅い
- お気に入りのおもちゃでしか遊ばない
- 約束事をすぐ忘れる
- 気に入らない事があると怒ったり泣く、パニックになる
このようなチェックにあてはまると知的障害の可能性があります。
しかし、「知的障害があるとあてはまること」にあてはまっても、必ずしも知的障害とは限りません。
2歳児の発達には個人差があります。
そのため、周囲が成長を温かく見守りながら子供が1人で出来ることを増やしていきましょう。
子育ても1人でするのは大変です。
周囲に協力してもらいながら行いましょう。
周囲の目があれば、自分1人ではなく、関わった人が気づく可能性もあります。
もしも、子供の発達に不安を感じたりおかしいと思うことがあれば専門家に相談してみましょう。
関連記事

2022.09.29
《福祉コラムVol.19》知的障害児とは?幼児期からの行動特性なども詳しく解説!
小さい子どものうちでも、知的障害の診断を受けることができます。 知的障害とは、発達期(18歳以下)までに生じた知的機能障害により、認知能力の発達が全体的に遅れた水準の状態をいいます。 診断を受けた子た[...]

2022.11.22
《福祉コラムVol.49》自立訓練とは?対象者や期間・料金、事業所の種類など解説。
「自立訓練」は、あまりなじみのない言葉ではないでしょうか。しかし、障害者にとっては日常生活を送れるようになる大切な言葉であり、必要不可欠な訓練です。「自立訓練」とは具体的にどんなことをするのでしょうか[...]

2022.08.13
《福祉コラムVol.12》軽度知的障害児の特徴と成長
軽度知的障害児をご存知でしょうか。 成長の過程で、どのような様子がみられるのでしょうか。 どこに困り事があり、どのような支援が必要なのか、就学後の配慮なども含めてまとめていきます。 軽度知的障害とは?[...]