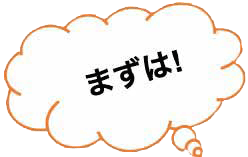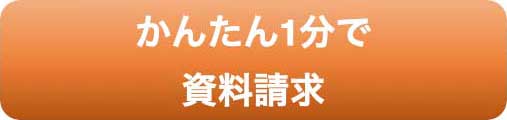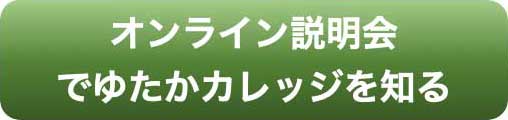《福祉コラムVol.49》自立訓練とは?対象者や期間・料金、事業所の種類など解説。
2022.11.22

「自立訓練」は、あまりなじみのない言葉ではないでしょうか。しかし、障害者にとっては日常生活を送れるようになる大切な言葉であり、必要不可欠な訓練です。「自立訓練」とは具体的にどんなことをするのでしょうか。対象者や期間・料金、事業所の種類などを解説します。
自立訓練が目指すこと
自立訓練によってどのようなことが身につくのか具体的にみていきましょう。
自立訓練とは?
自立訓練は「生活訓練」と「機能訓練」に分かれます。「生活訓練」と「機能訓練」は、障害者が日常生活を取り戻す意味からは目的が同じです。しかし、目的を達成させるためのやり方が異なります。自立訓練(生活訓練)は、基本的な日常生活で最低限必要になる動作能力を身につける訓練です。
訓練する動作能力には、
- ベッドから起き上がったり、座ったりができる
- 自分で歩行や階段の昇り降りができる
- 一人で入浴できる
- 自分で食事ができる
- 自分一人でトイレに行って排泄ができる
- 自分で着替えられる
などがあります。
ベッドから起き上がったり、座ったりができることは睡眠と起床に欠かせない大切な動作です。障害者が自分で食事ができるようになるには、口に運ぶことやスプーンや箸の使い方などの訓練が必要になるでしょう。
このように障害者が自立した生活が送れるようにするのが自立訓練(生活訓練)。
一方で自立訓練(機能訓練)は、障害者がスムーズな動作ができるように身体能力を訓練することです。つまり、自立訓練(機能訓練)の方が先の訓練と言えるでしょう。
自立訓練のサービス対象者と期間
ここでは、自立訓練(生活訓練)のサービス対象者と利用期間や料金と利用手続きの流れなどを解説します。
自立訓練のサービス対象者
自立訓練(生活訓練)のサービス対象者は、自立訓練(機能訓練)を終えて生活に必要な動作能力が必要な障害者。例えば、病院を退院した方や心身に障害のある児童・生徒が通う特別支援学校を卒業した方などが対象です。
自立訓練の利用期間と利用料金
自立訓練(生活訓練)のサービスを利用するには、市区町村から発行される「障害福祉サービス受給者証」を取得する必要があります。サービス利用期間は2年間。しかし、市区町村に申請して認められれば2年以上も可能です。
サービス利用料金は、利用者とその世帯の所得に応じた「応能負担の原則」で決まります。
負担額
- 所得(300万円以下)や生活保護を受けている世帯0円
- 所得(600万円以下)9,300円
- それ以外37,200円
自立訓練の利用手続きの流れ
- 自立訓練(生活訓練)のサービス利用の流れは4ステップ。
- 住んでいる市区町村の(障害福祉窓口など)へ相談
- 見学・体験
- 「障害福祉サービス受給者証」の発行手続きをする
- 利用開始
自立訓練(生活訓練)を利用したいと考えたら市区町村の(障害福祉窓口など)へ相談
することがスタートです。相談すれば事業所ごとのプログラム内容や雰囲気の違いなどの情報が得られます。事業所を決めたらどのようなプログラムが受けられるのか、自分に合っているのかなど見学・体験を申し込みましょう。
見学・体験で事業所を決めたら「障害福祉サービス受給者証」の発行手続きを進めます。発行されるまで1〜2ヶ月ほどかかり、発行されたら事業所と契約すれば、利用できます。
自立訓練の事業所の種類
ここでは通所型・訪問型・宿泊型の自立訓練(生活訓練)事業所の種類についてみていきましょう。
通所型
事業所に通って自立訓練(生活訓練)を受けるのが通所型です。朝から夕方まで行うことが多く、規律正しい生活を身につけやすいと言えます。
訪問型
障害者宅にスタッフが訪れて自立訓練(生活訓練)を実施するのが訪問型です。事業所に通う必要がなく、歩行が困難な方や多くの人と出会うことが苦手な人に向いていると言えます。
宿泊型
昼間サービスが受けられない人を対象にして支援するのが宿泊型の自立訓練(生活訓練)です。夜間の訓練になるため入浴や着替えなどの自立訓練(生活訓練)がしやすいと言えます。また昼間時間がとれない人には便利です。
自立訓練のプログラム内容
ここでは、具体的にどんな訓練をするのか以下のプログラムの内容について解説します。
プログラム
- 日常生活に必要な能力を高める
- 自己管理できる精神面をつくる
- コミュニケーション能力の向上
- 地域のマナーやルール生活への移行支援
自立訓練:日常生活に必要な能力を高める
日常生活に必要な能力
- 食事:スプーンやフォーク、箸を使って自分一人で食べるのかなど
- 排泄:トイレで排尿や排便が一人でできるかなど
- セルフケア:顔を洗ったり、歯磨きをしたりできるかなど
このように日常生活に必要な行動ができるように支援します。
自立訓練:自己管理できる精神面をつくる
自己管理できる精神面をつくるのは、自分のことを理解するようになるための訓練です。
訓練内容
- 自分の障害や特性(できないこと)を理解する
- ストレス発散方法やリラックスできる方法を身につける
自立訓練:コミュニケーション能力の向上
この訓練では、他の人への挨拶・返事の大切さを学びます。また、他の人の意見を聴き、何を言いたいのかが、わかるようなスキルと自分の考えや思いを伝える訓練をします。
自立訓練:地域のマナーやルール生活への移行支援
ここでの主な訓練内容
- 地域生活に欠かせないマナーやルールを守るための訓練
- バスや電車などや銀行、郵便局、市役所などが利用できる訓練
- 病院を受診する訓練
まとめ
自立訓練は障害者や病院を退院した人たちが日常生活ができるようになるための大切な訓練です。自立訓練を受ける時には、市区町村の(障害福祉窓口など)に相談して「障害福祉サービス受給者証」を発行してもらう必要があります。自立訓練の流れや事業所の種類などを知り、スムーズに受けられるようにしましょう。
関連記事

2022.10.25
《福祉コラムVol.34》知的障害は治る?治療や能力を伸ばす接し方について解説!
発達期まで発症した知的機能の障害によって、認知能力や生活能力が一般的な水準と比較して遅れをとっている状態を、知的障害と定義します。 ただ物事を理解して考えるといったIQの低下のみならず、生きていくうえ[...]
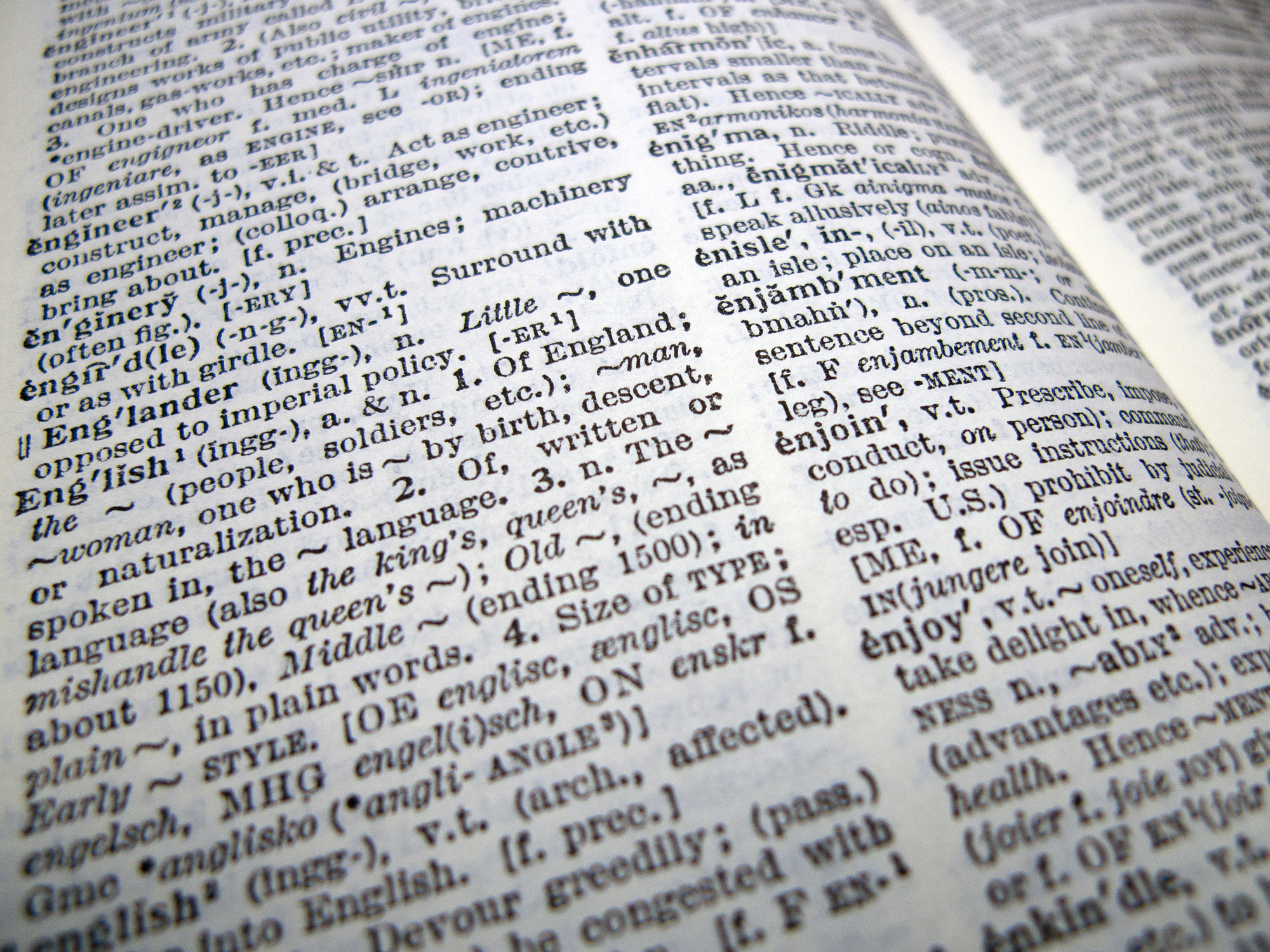
2022.11.07
《福祉コラムVol.42》知的障害者の定義とは?判断基準や診断方法などを紹介!
知的障害者という言葉を聞いたことはありますか?知的障害者とは、18歳までに知的機能の低下が生じ、日常生活や社会生活に困難さを抱えている方をいいます。聞いたことがない方もいるかもしれませんが、我が国では[...]

2022.10.27
《福祉コラムVol.36》知的障害児との接し方とは?特徴とそれに併せた接し方を解説!
知的障害児という言葉を聞いたことがありますか?知的障害とは「18歳までに知的機能の低下により、日常生活や社会生活に困難さが生じる状態」をいいます。そして、知的障害児とは「知的障害のある18歳未満の者」[...]