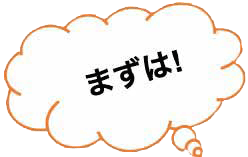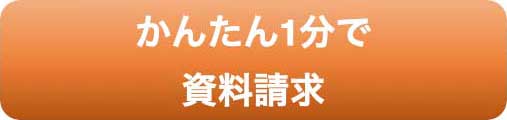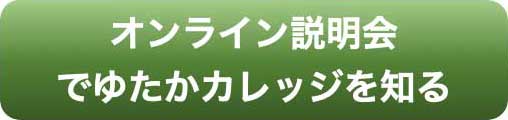《福祉コラムVol.36》知的障害児との接し方とは?特徴とそれに併せた接し方を解説!
2022.10.27

知的障害児という言葉を聞いたことがありますか?知的障害とは「18歳までに知的機能の低下により、日常生活や社会生活に困難さが生じる状態」をいいます。そして、知的障害児とは「知的障害のある18歳未満の者」を指します。ここでは、知的障害児の特徴や接し方について詳しく紹介していきます。
知的障害児の特徴
知的障害児は知的機能の低下によって「理解力・表現力の乏しさ」「注意力・集中力の低下」「記憶量の少なさ」などが生じます。日常生活のなかでも多種多様な行動が生じますが、ここでは、多くの知的障害児に共通する3つの特徴をご紹介します。
①学習が難しい
小学校に入学すると授業が始まり、国語(書字や読字)や算数など必要な学習を行います。知的障害児の場合は知的能力の低下によってこれらを円滑に習得することが難しくなります。ただし、他の項目にも共通していえることですが、どの程度まで身に付けることができるかについては、知能指数や学習環境が大きく影響します。そのため、個人差があることに注意が必要となります。
②問題を解決することが難しい
問題を解決するためには抽象的思考や実行機能と呼ばれる能力が求められます。まず、抽象的思考とは「物事の共通点に着目し、一般的な概念でとらえる力」のことをいい、簡単にいうと、ざっくりと大きなまとまりで考える力を意味します。例えば「犬」を説明する場合にはどのような表現を用いるでしょうか?小さい子どもであれば「ポチ(飼い犬の名前)、トイプードル(犬種)」など具体的な名前を挙げることでしょう。一方で、大人であれば「四足歩行で歩く、鼻がよく利く動物」といったように犬全体の共通点である「四足歩行」「鼻の良さ」に着目した表現をすることでしょう。このような、共通点を見出してカテゴライズする力を抽象的思考といいます。
次に、実行機能とは余り聞き慣れない言葉ですが、簡単にいうと、「物事を組み立てる力」のことです。例えば、突然自宅に友達が遊びにくることになったとします。しかし、部屋はとても散らかっています。その場合、あなたはどうするでしょうか?「まずは洗い物をして、次に掃除機をかけて…」といったように掃除の優先順位を考えながらやるべきことを整理しますよね。この力を実行機能といいます。
これらは通常、小学校高学年頃(12才頃)から身に付き始める力になりますが、知的障害児の場合には、年齢を重ねても計画を立てたり、優先順位をつけることが難しく、決まったパターンでしか問題を解決できない場合があり、支援を必要とすることが少なくありません。
③コミュニケーションが難しい
言葉の意味が理解できなかったり、適切な表現を用いることが難しい場合があります。そのため、友達と遊ぶ時にルールを守ることができなかったり、相手が訴えている内容を理解できなかったりとコミュニケーションを取る場面でトラブルが生じてしまうことがあります。特に、「あれ」「これ」「それ」といった曖昧な表現を不得手としており、実はどのことを指しているのか分からないまま返事をしてしまう場合も多々、見受けられます。
コミュニケーションが上手くとれないことでフラストレーションが溜まり、自身の気持ちを上手く伝えられないもどかしさと相まって、衝動的な行動に至ってしまうこともあります。
知的障害児との接し方
①しっかりと話しを聞く
知的障害児の多くは、質問をしたり、自分の気持ちを表現することを苦手としています。しかし、うまく表現ができないだけで、多くの子どもが何かしらの方法で気持ちを伝えようとしています。そのため、時間に余裕をもち、ゆっくり、しっかりと話しを聞く姿勢をもちましょう。文章になっていない場合でも、単語からその言葉の意味を推察することで本人が伝えたい気持ちを理解することができます。また、言葉での表現が難しい場合でも表情や行動から現在の気持ちを推し量る姿勢をもつようにしましょう。
②わかりやすく伝える
言葉や計算など学校の授業内容を理解することは難しい場合もありますが、本人の理解できる表現や方法を用いることで着実に理解を促すことができます。具体的には、「あれ」「これ」「それ」といった曖昧な表現を避け、具体的に伝えるようにしましょう。この時、簡潔かつ明確に伝えると、内容の理解を促しやすくなります。言葉での理解が難しい場合には、写真やイラストを用いることも、有効です。
問題が生じたときに混乱してしまう場合には、イラストや写真を活用した手順書を作成するのも有効な方法です。これによって、自分が「いつ、何を、どうすればよいか」が分かるので安心して活動に取り組むことができるようになります。
③ほめて自信を促す
知的障害児の多くは幼い頃からの失敗体験により、自信を失ってしまっています。自信を失うことで新しいことに挑戦する意欲が持てなくなってしまいます。そのため、できなかったことを責めるのではなく、頑張ったことを認め、ほめることが成長を促すことに繋がります。また、周囲の子ども達と同じようなことを求めるのではなく、本人の能力でできる遊びや活動、課題を促すことが成功体験と自信に繋がっていきます。
ほめる際には、具体的に伝えることが重要になります。「すごいね!」と伝えるだけでも良いのですが、「〇〇できて、すごいね!」と伝える方が、本人としては褒められている事柄を具体的に理解することができるようになります。また、ほめる際には、本人の年齢に応じた言葉遣いをするようにしましょう。悪気がなかったとしても、余りにも幼稚な表現を使ってしまうことで本人の自尊心を傷つけてしまう危険性があります。
まとめ
いかがでしたか?ここまで知的障害児の特徴と接し方を紹介してきました。これまでの内容をまとめます。
①知的障害児とは「知的障害のある18才未満の者」をいう。
②知的障害児の特徴には「学習の難しさ」「問題解決の難しさ」「コミュニケーションの難 しさ」がある。ただし、できること・できないことには個人差があることに注意が必要。
③知的障害児と接する際には「しっかりと話しを聞く」「分かりやすく伝える」「ほめて自 信を促す」ことが大切。これらを心掛けることで成長が促されやすくなる。
関連記事

2022.10.04
《福祉コラムVol.22》2歳児の知的障害はどこでわかる?チェックリストで紹介
「知的障害はどこでわかるのでしょうか」 「どんな症状なのだろう」 言葉は聞いた事があるけど、内容まで詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか。 特に小さなお子さんがいる人は、特に気になるでしょ[...]

2022.10.11
《福祉コラムVol.26》知的障害とは?その認定の時期についても詳しく解説!
知的障害と一概に言っても、人によってその程度や症状は様々ですよね。 知的障害者の方にはどういった特徴があり、また、いつどのように判断されるのでしょうか。 この記事では、 ・知的障害の特徴にはどのような[...]

2022.08.02
《福祉コラムVol.3》知的障害の人に多く見られるダウン症
ダウン症とは、染色体の異常から発症するダウン症候群という先天性の疾患です。ダウン症の多くは知的障害との合併を伴い、さまざまな身体的異常が見られるのが特徴です。 ダウン症候群という名称は、1965年に世[...]