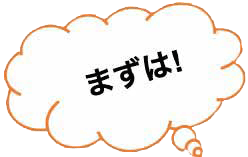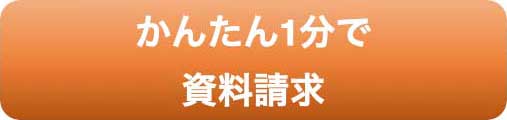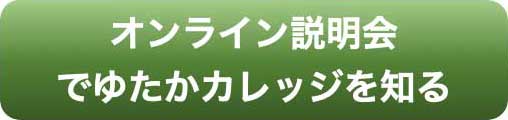知的障害者に学びの機会と喜びを
2022.06.09

知的障害者は健常者と比べて離職率が高い

健常者の7割が大学や専門学校に進学する時代、知的障害者の高等教育進学率はわずか0.7%という低い数字だ。ほとんどの知的障害者は18歳で企業に就職するか、福祉サービスの事業所で作業する。働くことの意味もよくわからず、社会人としての社会性やコミュニケーション力、感情コントロールも育っていない18歳の知的障害者に学ぶという選択肢がなく、働くという選択肢しか存在しないのが今の日本の現状である。その結果、職場で起こる様々なことにうまく対応できず、離職してしまう。知的障害者の就職1年後の離職率は32%、これは健常者の約3倍の数値だ。
世界では知的障害者のための学び場がある

世界では、大学の中に知的障害者の履修コースの設置が認められている。その契機となったのが、2006年に国連で採択された障害者権利条約だ。同条約第24条(教育)に「障害者が差別なしに一般的な高等教育を享受することができることを確保する」とうたわれ、知的障害者の高等教育を受ける権利が明確化された。
日本でも知的障害者のサポート校が存在する

「ゆたかカレッジ」は、知的障害者のための高校卒業後の4年間の学びの場だ。とはいえ、正式な学校ではなく、障害者福祉制度を活用した疑似大学である。2年間の自立訓練サービスと2年間の就労移行支援サービスを組み合わせ、1、2年生は経済、労働、ヘルスケア、スポーツ、文化芸術などを学び、3年生からは店舗や事務、清掃などの実務を学んでいく。
特別支援学校の高等部でも職業教育をしているが、何もわからないまま就職のレールに乗せられるのではなく、働く動機を見つけ、育てることが必要だ。カレッジでの4年間は、教育だけでなく、ゆっくり自分で考える時間として重要なのである。
近隣の学校と提携して知的障害者の支援をしている

ゆたかカレッジでは、近隣大学との共同研究やパイロット事業として、歴史学や哲学、課題研究などの授業を行ったり、レクリエーション活動や地域清掃ボランティアなどを通じて、同世代の一般学生との交流も深めている。現在、東京、神奈川、千葉、埼玉、静岡に合計9校を設置しており、約350人の知的障害者が通い、仲間たちと様々なことを学び、青春を謳歌している。学生たちは、好きな英語から海外に興味を広げたり、「絵が好きなのでポスターのデザインをやってみたい」と仕事にも夢を膨らませていく。
知的障害者がサポート校を卒業した後のその後

そして、4年生になると、いよいよ就職に向けて企業でインターンシップを行う。これまでの卒業生118人の就職率は72%、職場定着率は89%だ。
ゆたかカレッジは、今後も知的障害者の学びの場を全国に広げていきたいと考えている。
関連記事

2022.10.14
《福祉コラムVol.29》4歳児の知的障害はどこでわかる?チェックリストで紹介
「4歳児になったけど、まわりと少し発達がゆっくりなような…」、「まわりの子と少し違うような」などと思う保護者も多いはずです。 まわりと少しでも自分の子が異なることをしていると、気になりますよね。 発達[...]

2022.11.25
《福祉コラムVol.51》一人暮らしに必要な最低の資金とは?始める時の初期費用について解説。
一人暮らしを始めたいけど必要な資金がわからず断念する人もいるのではないでしょうか。一人暮らしがスムーズにできるように必要な資金の費用別の種類と金額について解説します。また一人暮らしに向いている物件や一[...]

2022.11.30
《福祉コラムVol.54》自立訓練の生活訓練は機能訓練と何が違う?行う内容についても解説
自立訓練には生活訓練と機能訓練の2種類があります。この2つは目的が違うため別々に分けられていますが、その目的や対象者はどう違うのでしょうか。しっかり把握していないと、いざ自分や家族が受けることになった[...]