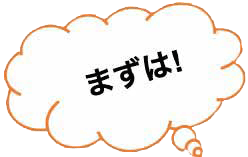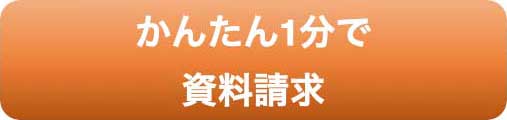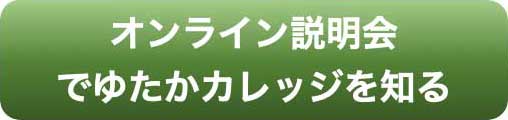《福祉コラムVol.54》自立訓練の生活訓練は機能訓練と何が違う?行う内容についても解説
2022.11.30

自立訓練には生活訓練と機能訓練の2種類があります。この2つは目的が違うため別々に分けられていますが、その目的や対象者はどう違うのでしょうか。しっかり把握していないと、いざ自分や家族が受けることになったとき、どちらを選べばいいのか分からなくなってしまいますよね。そこで今回は両者の違いと詳細について解説します。
自立訓練には生活訓練と機能訓練がある
自立訓練をおおまかに分類分けすると、生活訓練と機能訓練の2種類に分けられます。自立訓練は、障害を持った人が自立して生活できるようにするための訓練ですが、生活と機能は一体何が違うのでしょうか。まずはこの項目で詳しく確認していきましょう。
生活訓練は生活能力改善が目的
生活訓練は、自立して日常生活を送るために必要な行動ができるように支援や訓練を行います。障害がなければ簡単にできることでも、スムーズにできないことが障害者のなかにはたくさんいるでしょう。人によって抱えている障害の内容は異なるため、その人のできないことのサポートを専門のスタッフとともに行います。
たとえば、食事を作るといったことはハンデがなくても苦手という人は多いでしょう。しかし脳や体にハンデがある人の場合は、本格的に料理を作るだけでなく電子レンジでお惣菜を温めることも難しい行動かもしれません。
そのため、そういったことが苦手な人には電子レンジの使い方を覚えてもらう必要があり、それをスタッフと相談しながら練習していくことになるでしょう。
機能訓練は身体機能改善が目的
一方、機能訓練は日常生活をするうえで必要な身体機能の向上を目的としています。たとえば、体に障害があり日常生活の動作で困難な部分があるなら、その部分のリハビリが必要ですよね。
そのため、機能訓練は身体に障害のある人の申込みが大多数です。必要なリハビリの内容も人それぞれで違うので、生活訓練と同様にこちらも専門のスタッフに相談しながら、個別に訓練内容の計画を立てて行います。
自立訓練(生活訓練)で行う内容と対象者
では具体的にどのようなことを行うのか、そしてどんな人が該当するのかについてみていきます。この項目では、生活訓練にスポットを当てて確認していきましょう。生活訓練でする内容は以下のものです。機能訓練はこれらを行うときに必要な身体のリハビリなので、詳しい内容は省略していきます。
【生活訓練で行う内容】
- トイレや入浴
- 食事を作る、食べる
- 部屋の整理整頓、片付け
- ゴミ出しなどの衛生管理
- 公共施設(スーパーや銀行)の利用
- 公共機関(電車や車)での移動
- お金の管理
- 自分の体調の管理
- 他人や地域との交流
これらの行動は、どれも家族と暮らすにしろ一人暮らしをするにしろ、生きていくうえで必要となってきますよね。健常者であっても、完璧に全てこなせるのかと言われると難しいかもしれません。
行う内容はプログラムごとに違う
「自立した生活」と一言で言っても、人によって目指している生活の程度の差はでてきます。そしてAの行動はできるけどBの行動はできない、別の人はAは少ししかできなくてBはできるなど、障害によっても人それぞれです。
したがって自立訓練では、訓練を受ける人と話し合いながらプログラムの内容を決めていきます。これは一度決定したら変更不可というわけではありません。実際に取り組んでみたら、別の問題に気づいたからプログラム内容の変更が必要ということもあるでしょう。利用者の状態・状況にあわせて、臨機応変に変更しながら訓練を実施していきます。
自立訓練(生活訓練)が必要となる人
訓練対象となる人は、日常生活をする際に必要な能力が落ちている障害者です。障害があると治療のために病院に入院したり施設で生活している場合が多いかと思います。体に不自由なところがない健常者も、けがをして数週間や数ヵ月の間入院でもすれば筋力が落ちますよね。
その状態でけがをする前の生活をしようと思ってもいきなりはできません。退院前に歩行練習だったりさまざまなリハビリを受け、ある程度回復したらやっといつもの生活に戻れますよね。
それと同じで、自立して生活するときに欠かせない能力を鍛えたり維持したり、あるいは助言が必要な人は受けたほうがいいでしょう。これ以外としては、病気や障害の症状が落ち着いている人や通院期間が終わっている人、特別支援学校を卒業している人などが条件に入ります。
自立訓練(生活訓練)を受ける場所
受ける場所は全国にある自立訓練事業所です。プログラム内容はその事業所で決めることになるので、事業所が行っている取り組み内容から選択していくことになります。そのため自分が受けたいものを行っているかどうか、利用前に確認しなければいけません。
自立訓練(生活訓練)事業所の種類と特徴
自立訓練はそれぞれの事業所で受けられることが分かりました。ネットでも簡単に事業所を検索でき、事業所は全国にたくさんあります。しかし、実際にどのような事業所を選べばいいのでしょうか。続いては、事業所の種類と特徴についてみていきます。自分が住んでいるエリアで適した事業所選びの参考にしてみてください。
自立訓練(生活訓練)事業所の種類
おおまかな種類は以下のとおりです。
- 自分が事業所へ通う
- 自宅へ訪問してもらう
- 施設に泊まる
- 複合タイプ
注意として、これらは全国にある事業所全てで行われているわけではありません。自分から通う形でしかやっていないところも地域によってはあります。利用を検討中の人はそのあたりも確認しておきましょう。それでは、それぞれのタイプにどのような特徴があるのか、次の項目で一つずつ説明していきます。
自立訓練(生活訓練)事業所の特徴
まず1つ目の、自分から事業所へ通うタイプは、施設や病院へ行くのと同じような流れです。昼間に行って夕方くらいに帰ります。事業所まで家族に送ってもらったり自分で通ったりと、特にほかの希望がなければこのパターンが利用しやすいでしょう。自宅が事業所の近くという場合にもおすすめです。
2つ目の訪問タイプは、こちらから通うのが難しい場合に適しています。歩くのが不自由だったりたくさん人がいる環境に慣れていなかったりする人向けです。訪問であれば自分と来てもらったスタッフのみとのコミュニケーションなので、自立に向けて人との交流能力を向上させたいときに、訪問型から通所型へ移行していくのもいいでしょう。
3つ目の施設に泊まるタイプは、夜の時間帯に訓練を受けたい人に適しています。日中は仕事をしていたり別の施設に通っていたりすると、訓練を受けたくても受けられませんよね。そのような際に、他者との共同生活にはなりますが、事業所に泊まる形で利用できます。
最後4つ目の複合タイプは、自立訓練以外の福祉支援も行っている事業所です。たとえば、仕事に就くための支援を受けつつ、生活訓練も受けるといった形になります。どのような支援活動を行っているか、これらは各事業所によって異なるため、地域によっては希望の事業所が遠いという場合もあるでしょう。
まとめ
自立訓練には生活訓練と機能訓練があり、どちらも一般的な日常生活を営むうえで必要になる能力の維持向上や訓練を行います。障害を持っていると、生活するときに生じる悩みや課題も大きく、自立した生活なんて自分には一生できないと考えてしまうかもしれません。しかし全国には助けとなる福祉事業所が数多くあります。対象者の条件をクリアしていれば利用可能なので、支援制度をうまく活用しつつ、自立に向けて立ちはだかる問題を解消させていきましょう。
関連記事

2022.11.03
《福祉コラムVol. 40》知的障害児の療育方法とは?改善することはできる?
知的障害児は知的発達の遅れがあることで、言葉や運動能力の遅れが見られるなど特別な支援が必要になります。 そのため、幼児期に専門機関で適切な療育を受けることは、子供の成長の大きな手助けになります。 では[...]

2022.10.24
《福祉コラムVol.33》知的障害児の出生率は?男女比率やダウン症の出生率も併せて解説!
知的障害は、出生前に発生する遺伝子的要因により発生するケースが多くあります。 もちろん障害が軽度であるため大人になってからも気づかない場合も存在していますが、生まれる前の環境や状況によって発症すること[...]

2022.08.09
《福祉コラムVol.9》重度知的障害者とは?
重度知的障害者は、どんな人のことを示すのかご存知でしょうか。 どのような特徴があり、介助や支援が必要なのでしょうか。 また、重度知的障害と診断がおりた場合どのような福祉サービスや、サポートを受けること[...]