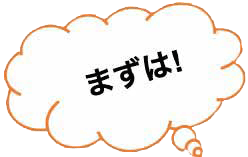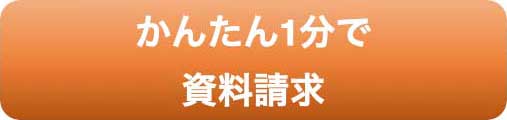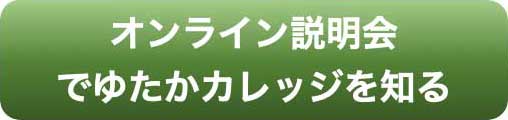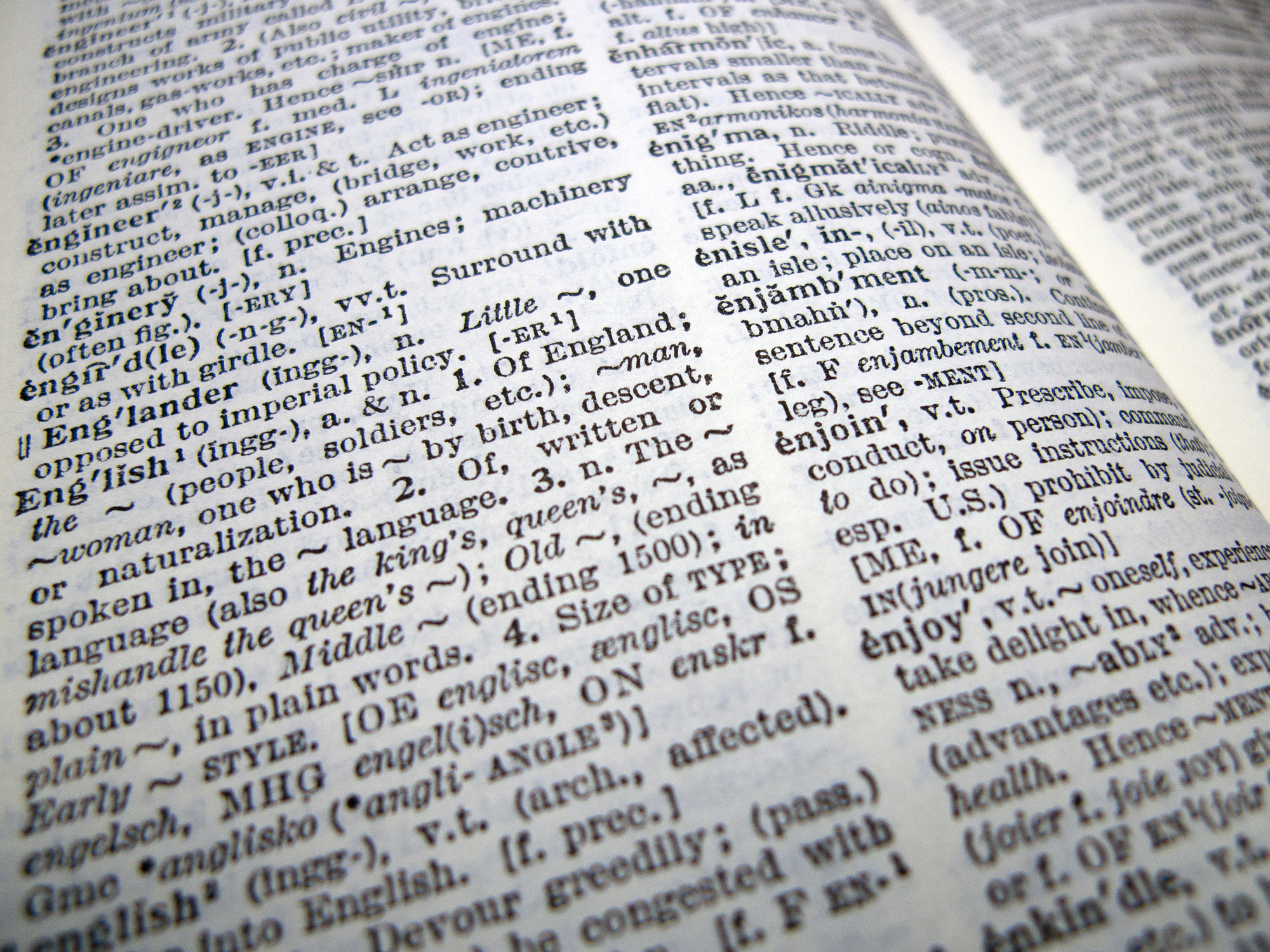《福祉コラムVol.46》知的障害者の福祉法においての定義とは?
2022.11.16
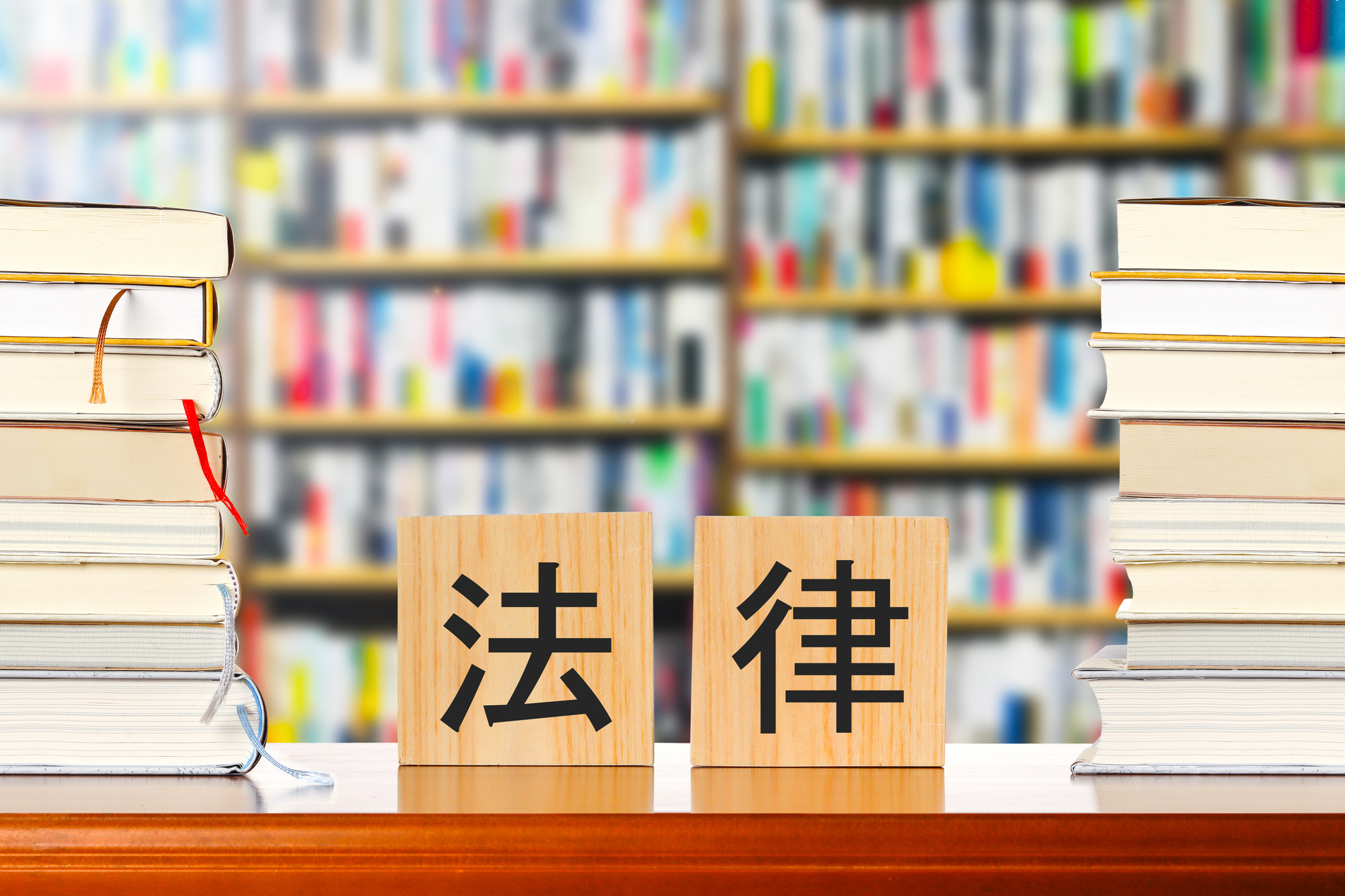
知的障害という言葉の認知度は高くなっております。
福祉に従事していない人でも、言葉として知っている方も多いはず。
誰もが知っている知的障害ですが、法律ではどうなっているのでしょうか。
知的障害者を示す法律、福祉法にはどのように定義されているのでしょうか。
こちらの記事でまとめていきます。
知的障害の原因
知的障害の原因は一つだけに限定されるものではありません。
脳障害を引き起こす疾患や、要因などすべてが原因となる可能性が高いと考えられています。
原因となるものは、十分に解明されていませんが、最近の遺伝子研究から主な要因が考えられます。
- 病理的要因
- 生理的要因
- 環境要因
の3つの側面から分類できると考えられています。
知的障害者の福祉法においての定義
知的障害者福祉法は、知的障害のある人の自立と社会参加を促進するよう法律で定められているものになります。
しかし、福祉法においてどのようなものを知的障害と指し示すのか定める規定がないのです。
このため、医学、心理学、教育学などの領域でそれぞれの定義が定められているのです。
呼び名も、その定めている分野によってばらばらなのです。
この知的障害という名称自体が、学校教育法や児童福祉法などの法律で使用されてから、日常的に使われるようになりました。
まとめ
知的障害者の福祉法についてまとめていきます。
- 知的障害の原因はまだ解明されておらず、一つだけに絞ることができない。
- 知的障害の要因として「病理的要因」「生理的要因」「環境要因」の3つの側面から分類できる。
- 知的障害者について、福祉法では明確な定義はない。各分野で呼び名が異なり、統一はされていない。
- 知的障害者という言葉は、児童福祉法や学校教育法の法律で使用されてから呼ばれるようになった。
障害者が自立と社会参加を促進するよう法律で定められていますが、一方で知的障害を持っている人に対する定義は明確ではありません。
法律で明確にされる日が早く来るとよいですね。
関連記事

2022.11.08
《福祉コラムVol.43》知的障害者の赤ちゃんの兆候を紹介
これから生まれてくる自分の子どもに、何か病気や障害があるかどうか気になる方は少なくないでしょう。 知的障害は生まれつきの脳機能の障害で、IQや日常生活の適応スキルに応じて診断され、論理的思考や抽象的思[...]

2022.10.12
《福祉コラムVol.27》知的障害者の性被害。未然に防ぐための予防策を解説
知的障害者の性被害が、多く起こっていることをご存知でしょうか。 多く起こっているにもかかわらず、事件化されておらず世間的にも知られていないのです。 それは、法律による壁と知的障害者ならではの特性につけ[...]
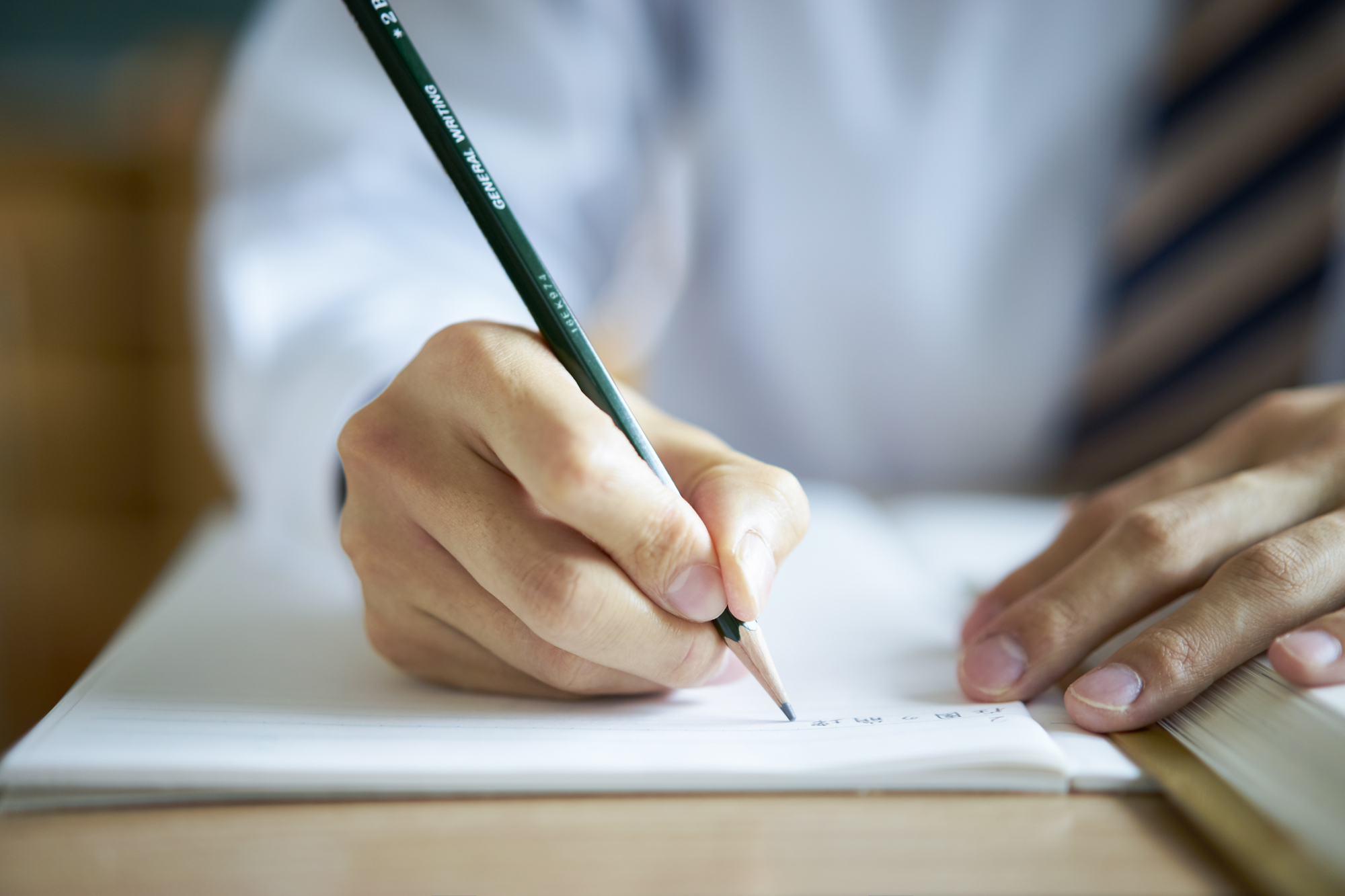
2022.11.17
《福祉コラムVol.47》知的障害に分類はある?定義や根本の原因などを解説!
知的障害にはどんな分類があるかみなさんご存知ですか? 大きく知的障害と言っても、まずは知的障害とはどんな障害なのだろうか。 こちらから説明していきます。 また、定義や根本の原因なども詳しく解説していき[...]