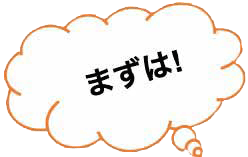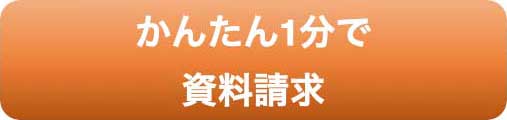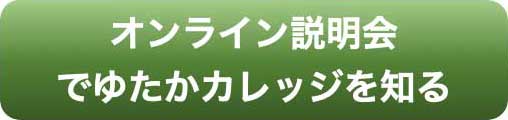《福祉コラムVol.37》知的障害者との接し方とは?特徴とそれに併せた接し方を解説!
2022.10.31

知的障害のある人と接するには、まず障害の特性や特徴について理解することが大切です。
ここでは、
・知的障害者の特徴にはどのようなものがあるのか
・知的障害者に出会ったらどのように接したらよいのか
についてまとめていきたいと思います。
知的障害者の特徴

知的障害者には、IQ(知能指数)の値の低さだけではなく、日常生活に適応するための様々な行動にも困難があります。
知的障害者には具体的にどのような特徴があるのか、いくつか代表的なものをみてみましょう。
複雑な話や抽象的な概念は難しい
・抽象的な思考や言葉を理解するのが難しい
・短期記憶の苦手さにより、一度にたくさんの情報を覚えたり処理したりすることが難しい
・自分で計画を立てたり、優先順位をつけることが難しく、問題の解決に固定化された方法でしか対処できないことがある
コミュニケーションが難しい
・言語的なコミュニケーションが難しかったり、相手の意図を正確に理解することが難しい場合がある
・自分から人にたずねたり、自分の意見を言ったりすることが難しい
・コミュニケーション面で特に困難な場合には、コミュニケーション障害や自閉症スペクトラム障害の可能性がある
読み書きや計算が難しい
・漢字が読めない、計算ができない場合がある
・お店などで合計金額を言われても、どの種類のお金が何枚必要なのかがわからないことがある
・時計が読めず、時間を言われてもわからない場合がある
ひとつの行動に執着したり、同じ言葉を繰り返したりしてしまう
・独り言を言っていたり、同じ言葉や行動を繰り返すことがある
・聞かれたこと、話しかけられた言葉をそのまま繰り返して言うことがある
・意味のないように見える行動にこだわってしまうことがある
急な予定変更や想定外のことに対応することが難しい
・つもりと違うことが起きたり、急に予定の変更があると、どうしたらよいかがわからない
・想定や思いと違うと激しく起こったり、パニックになったりする場合がある
特定の感覚が過敏または鈍麻
・大きな音や騒がしい場所が苦手でイヤーマフや耳栓を着用している場合がある
・苦手な感触があったり、人に触れられるのが極端に苦手なことがある
・痛みに鈍感で怪我をしても気付かない場合がある
・急に大きな音がしたり、苦手なものに触れたりすると、パニックになってしまうことがある
・感覚特性が特に強い様子がある場合は、自閉症スペクトラム症である場合が考えられる
このように、知的障害者の方は様々な困難を抱えています。
知的障害だけではなく、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)などその他の発達障害や身体障害を合併している方も多くいます。
日常の場面では、公共交通機関を利用するときに時刻表や行き先が分からない、買い物をするに欲しいものの場所や支払いの仕方が分からないなど、困っている様子を見かけることがあるかもしれません。
では、どのように支援したらよいのでしょうか?
知的障害者との接し方

簡潔に話しかける
・短い言葉で、ゆっくり優しく声をかける
・横や後ろからではなく、正面から話しかける
・何をすればよいのか具体的に伝える
・絵や写真等を使って伝えるとわかりやすい場合がある
相手の言うことによく耳を傾ける
・話すのに時間がかかる場合があることを理解して余裕をもって聞く
・文章になっていなくても、単語などから推測して伝えたいことを聞き取る
・質問をあまり理解していなくても「はい」と答えてしまうこともあるため、一つひとつ確認する
目的に合った方法や手段を教える
・ゆっくり一つずつ伝える
・抽象的な言葉「そこ」「あっち」等はわかりにくい場合があるので、具体的な言葉で、理解できているか確認しながら伝える
・大事なこと、ポイントは紙に書いて伝える
・場合によっては写真や絵を使って伝えるとわかりやすい
・金銭の受け渡しに関しては、お金の種類がわからない場合があるので、お金の種類と枚数を伝えるとよりわかりやすい
パニックになっているときは
・本人や周りの人が怪我をしないように危険な場所や物から遠ざける
・本人が落ち着くまで優しく見守る
・強引に移動を促したり、大きな声で話しかけたりするとかえってパニックを大きくする場合がある
・落ち着いてから優しく話しかける
これらのことに気を付けて関わっていても、支援することが難しそうな場合には、本人に了承を得て連絡先を聞き、家族や専門機関に連絡しましょう。
知的障害のある方は障害者手帳や名前や連絡先、障害の特徴などが書いたカード等を持っていることがあります。
まとめ
以上、知的障害者への接し方を特徴とともに紹介しました。
知的障害者の方は障害があることで、理解のない人に心無い言葉をかけられたり、ジロジロと見られたりすることもあります。
しかし、理解ある人の支援があれば、日常生活を送ったり様々な活動に参加することができます。
障害の有無に関わらず、お互いに支え合いながら生活できる社会にしていきたいですね。
関連記事

2022.06.09
知的障害を持つ学生が学び、自立を目指す福祉型カレッジ「ゆたかカレッジ」とは?
「大学」に見立てた福祉事業所 「ゆたかカレッジ」では、修業年限を4年とし、最初の2年間を自立訓練(生活訓練)事業、後半2年間を就労移行支援事業による就労に向けたトレーニングを行っています。障害者総合[...]

2022.09.15
《福祉コラムVol.14》知的障害児の出生原因とは?特徴や遺伝との関連性や診断について
知的障害児の出生原因にはどんな原因があるかご存じでしょうか。 知的障害児に関わったことがある方はいらっしゃいますか。 生活の中で関わったことのある方は少ないでしょう。 今後、生活の場面で関わることが出[...]

2022.10.04
《福祉コラムVol.22》2歳児の知的障害はどこでわかる?チェックリストで紹介
「知的障害はどこでわかるのでしょうか」 「どんな症状なのだろう」 言葉は聞いた事があるけど、内容まで詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか。 特に小さなお子さんがいる人は、特に気になるでしょ[...]